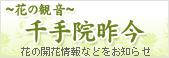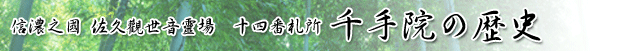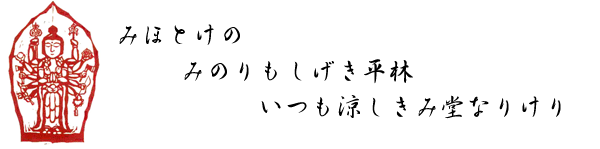
佐久十四番札所として、平林觀音さまで知られている千手院は、天台宗に属し比叡山を総本山とし、仁寿年間(紀元一五十一年頃)第三世天台座主を勤められました慈覚 大師「圓仁」の開基で、現在まで七十六代、一千百五十余年の法統を守る古刹であります。
山號を平林山、寺號を津金寺と称し、千手觀世音菩薩を本尊とし日本三津金寺の一寺です。日本三津金寺とは、北佐久郡立科町山部の津金寺、甲州津金の津金寺(現在の海岸寺)と當山の三箇寺で、ひとり寺號を同じくするのみでなく、ともに行基菩薩御手造りの三躰觀世音菩薩像を各々本尊としています。 千手院の前身は、はじめ蓼科山麓にあったとされ再三移転して佐久穂町栄地区小山澤(当時上村亦は神楽村ともいい、津金寺で神楽を演じたことからの地名という)に移り、室町時代の応永年中(紀元二〇五四年頃)栄地区の宿岩を経て、青沼村(現佐久市)十日町の東方木伐窪に移った。宿岩の地名も移転の際、巨岩の上に一時「本尊千手觀世音菩薩」を宿したので宿岩と改められたと伝えられています。現在佐久市十日町の道端にある六地蔵尊(現在国指定重要文化財)等も昔は千手院の大門先であり、十日毎に市場が開きなかなかに賑やかな町となったため十日町といわれています。
上村よりの移転は第二十六世法印「海傳」代で、木伐窪の淨蓮寺の境地に觀音さまを安置しました。その時に淨蓮寺を改め、平林山 津金寺 千手院と呼び、所謂 千手院の開山です。後年再三火災にみまわれ正徳年中(紀元二千三百七十一年頃)に木伐窪より現在の佐久穂町平林地区に移転されたもので、中世武田信玄が戦勝祈願と敵味方の戦死者の菩提を弔う為に田畑と永三十六貫文を寄付しており、境内には今なお、勝頼鎧掛けの松が参詣の善男善女に昔日の夢をかたらっています。
觀音さまは、慈悲の菩薩さまで世の中の苦しみの声(音声)をお聴きになる(観ずる)ので觀世音といい、男になるやら女になるやら 三十三にも身を変えて世の苦しみを救われるのです。この觀音さまには、六人の兄弟(聖、千手、馬頭、十一面、不空羂索、如意輪)があり、その中のお一人が千手觀音さまであります。千手觀音さまは、正しくは千手千眼觀世音菩薩といい、像形は普通両手両眼の外に左右各々二十本の手を備え、その掌の中に一眼づつを持っておられます。そしてこの一手一眼がそれぞれ二十五の働きをして世の苦しみを救われるので、四十手に二十五を乗じて千手となり、千眼ともなるのです。これは一切の衆生(人々)の苦しみを救われる無限の慈悲を現すものであり、諸願成就、現世利益のありがたい菩薩さまとして広く親しまれ信仰されております。